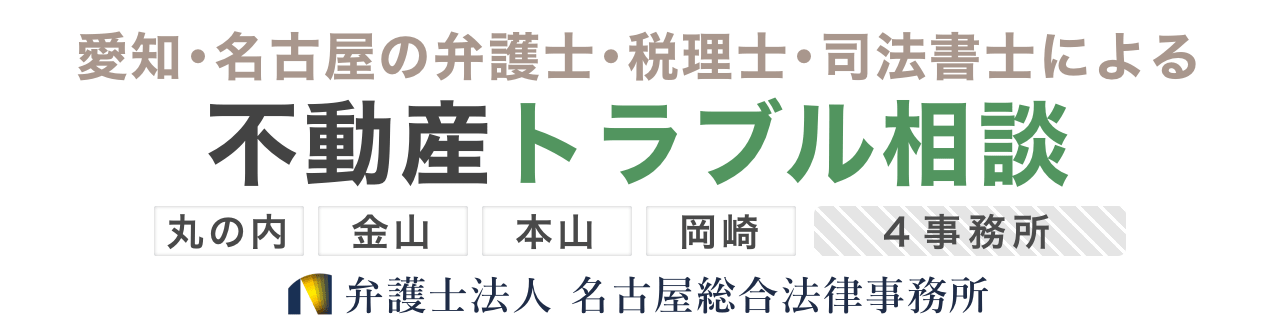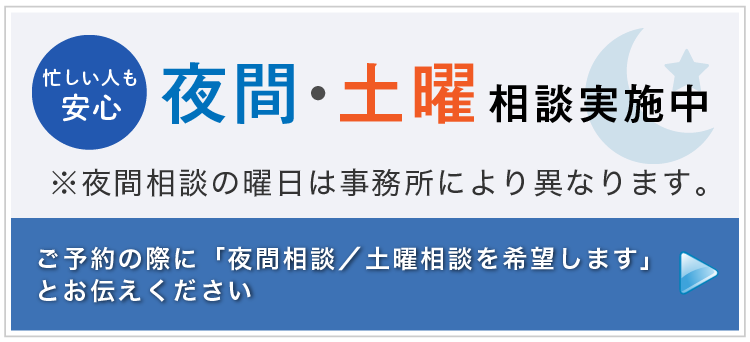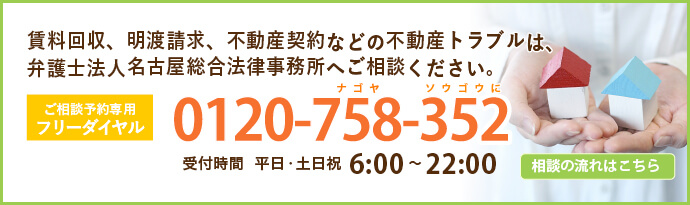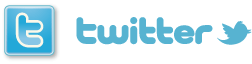賃料の減額を求められたら
賃料の減額請求権は、相手方に対する意思表示によって行使されます。実務上は、配達証明付きの内容証明郵便で行使されることが多く、突然相手方から賃料減額の書面が到達することも想定されます。
上記賃料減額請求権はいわゆる形成権であり、減額の意思表示をすれば、相手方がそれを承諾するか否かにかかわらず、将来に向かって、客観的に『相当』な金額に減額されるという効果が生じます。
そこで、その後は『相当』な額につき、相手と協議することとなります。
まずは『相当』な額を協議します
具体的には、まず相手方に対して、『相当』な額に関する資料を開示するよう要求するとともに、こちらもそれに関する資料を開示し、お互いの主張をぶつけ合って、『相当』な額のその落としどころを探っていくこととなるでしょう。
なお、賃料の減額請求について、減額請求を受けた者(貸主)は、減額を正当とする裁判が確定するまでの間、相当と認める額の賃料の支払いを請求することができます(借地借家法11条第3項、同32条第3項)。
この『相当と認める額』とは、従前の地代より高額であってはならないとされておりますが、賃貸人自身が主観的に相当と考える額を意味し、客観的な適正額を意味しないと解されております。
ただし、その裁判が確定した場合において、既に受領した額に超過分があるときは、その超過分に年1割の割合による利息を付してこれを支払わなければならないとされている点に注意が必要です。
つまり、賃料減額請求において、賃料の減額が認められた場合、賃貸人は賃借人に対し、その超過分に1割の利息を付してこれを返還しなければならないということです。
予防法としての特約
なお、上記のような賃料減額請求を予防するべく、「一定期間賃料を減額しない」旨特約しておくことも考えられます。
しかし、当該特約は、借地借家法上何ら認められておらず、当該特約は無効(すなわち、賃料減額請求権を行使しうる)と判断される可能性があるため、このような特約を設けているだけでは万全の対策とはいえないでしょう。
一方で「一定期間賃料を増額しない」旨の特約は有効なものとして借地借家法上も認められている点に留意しましょう(借地借家法38条7項)。
なお、平成12年に制定された定期建物賃貸借契約では、改定に借家特約がある場合には、借地借家法第32条(借賃増減請求権)の規定は適用しないとされています(同法第38条7項)ので、「減額をしない」という特約は、有効です。
いずれにしても、賃料減額請求を受けた時点で、直ちに専門家に相談した方がよろしいかと思われます。
土地・建物明渡トラブルについてさらに!