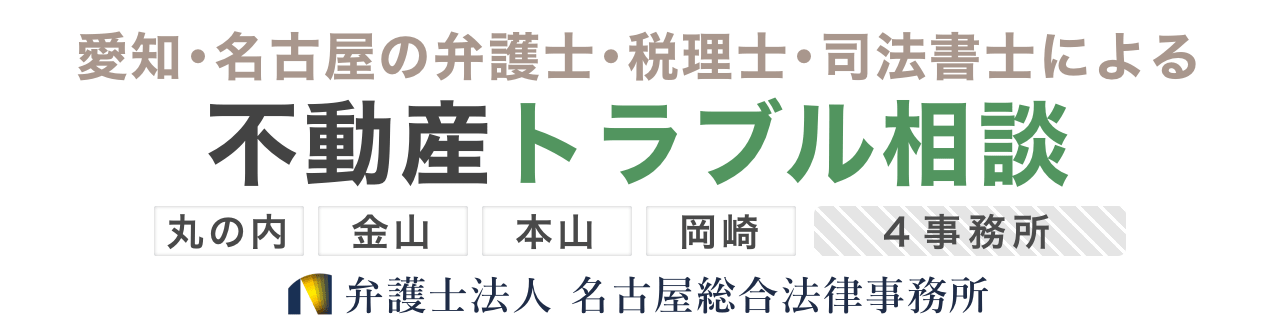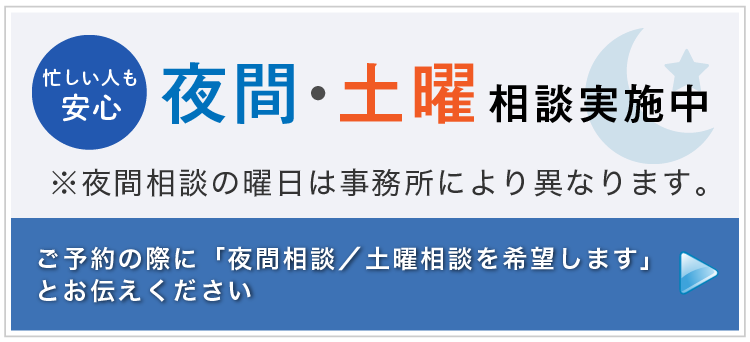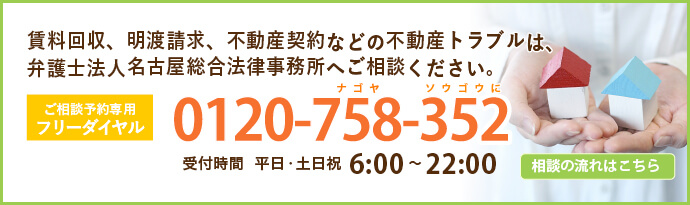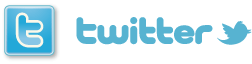時効
時効についての改正点
- ①消滅時効の起算点及び期間の見直し
職業別短期消滅時効の廃止
商事消滅時効の廃止
主観的起算点の導入
権利を行使できる時から10年、権利を行使できることを知った時から5年 - ②定期給付債権短期消滅時効の廃止
- ③生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
- ④不法行為に基づく損害賠償請求権の20年の期間制限は消滅時効
- ⑤中断・停止→更新・完成猶予に
更新事由・完成猶予事由
協議を行う旨の合意による時効の完成猶予 - ⑥援用権者について明確に
消滅時効の起算点及び期間の見直し

改正前民法
債権の消滅時効について、原則として「権利を行使できる時から10年」としつつ(改正前民法166条第1項、167条第1項)、職業別に短期の消滅時効を定めたり(改正前民法170条から174条)、商行為によって生じた債権については、時効期間を5年として、原則的な時効期間10年とは異なる時効期間を定めていました(改正前商法522条)。
↓時効期間をシンプルに統一化+主観的起算点を導入
改正法
・職業別短期消滅時効の廃止
・商事消滅時効の廃止
することで、時効期間を統一しました。
また、原則的な時効期間について、
主観的起算点を導入(166条第1項)し、
・権利を行使することができることを知った時から5年(主観的起算点)←追加
・権利を行使することができる時から10年(客観的起算点)
上記のいずれか早く到達する日に時効により権利が消滅することとなりました。
売買代金請求権や賃料請求権のように、契約によって生じた一般的な債権については、通常、権利発生時に権利行使が可能であることを認識していますので、「権利を行使することができるとき」(客観的起算点)と「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)は、基本的に一致します。そのため、改正民法では、これまで10年であった消滅時効期間が、5年に短縮されたに等しいことになります。
第166条
1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
定期給付債権短期消滅時効の廃止
改正前民法では、定期給付債権といって、年払いより短い期間で定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権については、5年間で時効により消滅するとされていました(改正前169条)。
たとえば、毎月支払われる賃料は、定期給付債権にあたりますので、請求できる時から5年で時効消滅していました。
↓シンプルに統一化
改正法では、上記定期給付債権の短期消滅時効についても廃止されました。そのため、毎月の賃料債権等についても、一律、権利行使することができる時から10年、権利行使することができることを知った時から5年で時効消滅することになりました。
ただ、前述のように、賃料債権も含め、契約から生じるほとんどの債権は、客観的起算点と主観的起算点が一致するため、5年で時効消滅します。そのため、根拠条文が変わるものの、時効期間は、改正前と改正後で変わりないといえます。
生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
改正前民法
人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については、他の債権と比べ、権利行使の機会を確保する必要性が高いにもかかわらず、特別な配慮がなされていませんでした。
改正法
改正法では、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権について、債務不履行に基づく場合には、権利を行使できる時から20年、不法行為に基づく場合には、損害および加害者を知った時から5年で時効消滅することとしました。つまり、生命・身体に対する侵害による損害賠償請求権については、債務不履行と不法行為のどちらに基づくものであっても、客観的起算点から20年、主観的起算点から5年の時効期間となります。
債務不履行に基づく損害賠償請求権→権利を行使できる時から10年
権利を行使できることを知った時から5年
不法行為に基づく損害賠償請求権 →不法行為の時(=権利を行使できるとき)から20年
損害および加害者を知った時から3年
↓特例
生命・身体の侵害による損害賠償請求権 →権利を行使できる時から20年
知った時から5年
第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
第724条の2
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
不法行為に基づく損害賠償請求権の20年の期間制限は消滅時効
改正前民法
不法行為に基づく損害賠償請求権の20年の期間制限が、除斥期間なのか消滅時効なのかで争いがありました。
除斥期間というのは、法律関係の速やかな確定を目的に設定された権利行使期間で、一定の期間内に権利の行使をしないと権利が消滅する期間をいいます。除斥期間の特徴としては、時効の中断や停止がなく、援用も不要で権利濫用等の主張の余地がないとされています。
この点、不法行為に基づく損害賠償請求権の20年の期間制限について、除斥期間であるとする判例がありました(最高裁平成元年12月21日)が、被害者救済の点で、問題があるとされていました。
改正法
不法行為に基づく損害賠償請求権の20年の期間制限は、消滅時効であることを法文上明らかにしました(724条2号)。
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
中断・停止→更新・完成猶予に

改正前民法には、時効の完成を妨げるための手段として、時効の中断及び停止という2種類の制度がありました。
ただ、改正前民法では、「中断」と「停止」という言葉が、必ずしも厳格に区別して使用されておらず、分かりにくい部分がありました。
そこで、改正法では、「中断」と「停止」の効果に着目し再編成するとともに、その文言も、より適切な表現である「更新」「完成猶予」と改めました。
更新:更新事由の発生によって、それまで進行した時効の期間が解消され無意味となり、その時点から新たな時効期間が開始する制度
完成猶予:時効の完成すべき時が到来しても、時効の完成を妨げる一定の事由が存在する場合に、その後一定期間が経過するまで、時効期間の完成が猶予される制度
時効の完成猶予事由・更新事由
①裁判上の請求等(147条)
裁判上の請求、支払督促、民事調停・家事調停、破産手続参加・再生手続参加・更生手続参加のいずれかの事由が生じると時効の完成が猶予されます。
そして上記手続きにおいて、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、更新され、ゼロから新たに進行します。この場合の時効期間は、10年となります(169条第1項)。
また、上記手続きにおいて、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合は、その終了の時から六箇月を経過するまで、時効の完成が猶予されます。
第147条
1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
②強制執行等
強制執行、担保権の実行、形式競売、財産開示手続きの各事由が生じるとその事由が終了するまで、時効の完成が猶予されます(148条第1項)。そして、各事由が終了した場合には、時効が更新され、新たな時効期間が進行します(148条第2項)。
ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによって各事由が終了した場合には、その終了時から6か月を経過するまで、時効の完成が猶予されます(148条第1項括弧書き)。
第148条
1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
③仮差押え等
仮差押え、仮処分の各事由がある場合には、その事由が終了したときから6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予されます(149条)。改正前民法では、時効中断事由とされていましたのでご注意ください(改正前民法154条)。
第149条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
④催告
催告があった時は、その時から6か月を経過するまでの間は、時効の完成が猶予されます(150条第1項)。
催告によって時効の完成が猶予されている間に、再度の催告をしても、かかる催告は、時効の完成猶予の効力を有しません(150条第2項)。
第150条
1 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
⑤承認
権利の承認があった場合には、時効が更新され、その時点から新たな時効期間が進行します(152条第1項)。
第152条
1 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
⑥協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
改正前民法では、権利をめぐる争いについて、当事者間で協議が継続していても、時効完成間際には、その進行を止めるため、訴訟提起などの手段を講じなければなりませんでした。そのため、改正法では、当事者間で、権利についての協議を行う旨の合意が書面もしくは電磁的記録によりなされた場合には、時効の完成を猶予するという制度を導入しました(151条)。
完成猶予の要件
①権利について協議を行う旨の合意
②書面または電磁的記録
→争いを避けるため、協議だけでは足りず、合意が必要となります。また、その旨を書面又は電磁的記録でする必要があります。
猶予の期間
次のうち、いずれかの事由が到来すると時効が完成します(151条第1項)。
①合意があった時から一年を経過した時
②合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
③当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
再度の合意
上記の期間が近づいてきたとしても、再度の合意をして、さらに時効の完成を猶予することができます(151条第2項)。また、かかる合意を複数回繰り返すこともできますが、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができません(151条第2項ただし書)。
催告との関係
催告があると、その時点から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予されます(150条第1項)。ただ、催告によって時効の完成が猶予されている間に、協議を行う旨の合意をしても、そのことによる時効の完成猶予の効力は生じません。
また、協議を行う旨の合意により時効の完成が猶予されている間にされた催告をしても、そのことでさらに時効の完成が猶予されるわけではありません(151条第3項)。
第151条
1 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。
第150条
1 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
第152条
1 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
援用権者について明確に
援用権者というのは、時効を主張して、時効の利益を得ることができる人のことです。
改正前は、文言上、時効の援用権者を「当事者」としているだけで、その意味するところが明確ではありませんでした。
ただ、この点については、解釈上も判例上も、「当事者」には、保証人、物上保証人、第三取得者が含まれると解されてきたことから、改正法では、
当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)
と記載し、これらの者も「当事者」に含まれることを明らかにしました。
第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
名古屋総合事務所の詳しい情報はこちら