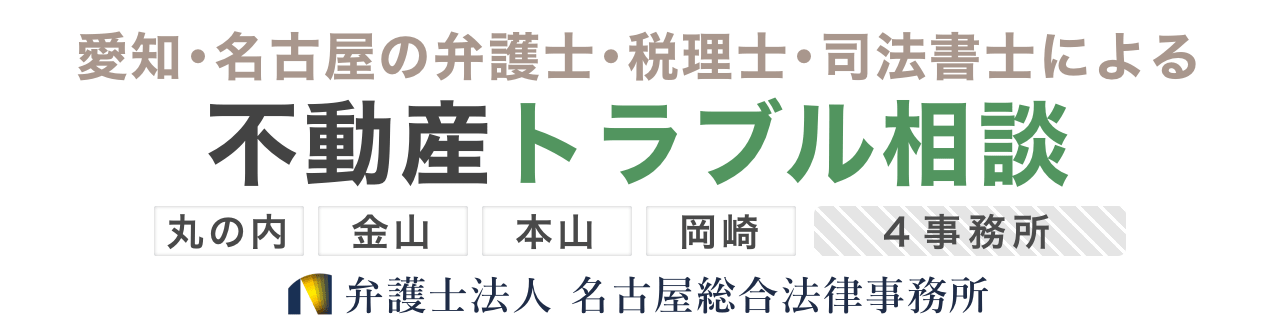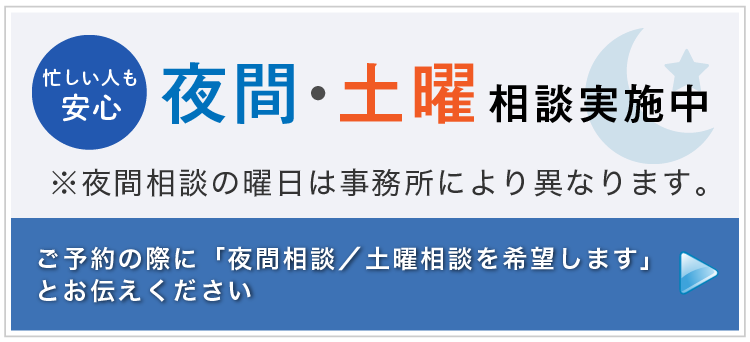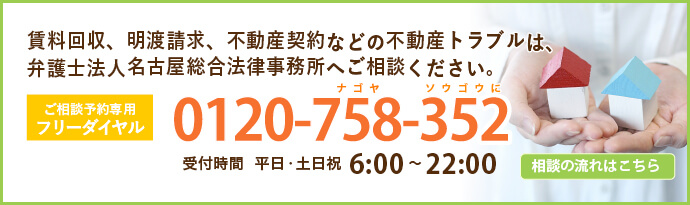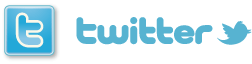老朽化した建物、どこまで修繕する必要がありますか。
建物を賃貸しているオーナーさんから、老朽化した建物の修繕費がかさんで大変だ、どこまで修理しないといけないのかという相談が多く寄せられます。
建物の老朽化が進んでいるものの、まだ建て直す程度にまでは至っていない物件について、どの程度の修繕をする必要があるのでしょうか。
賃貸人の修繕義務
建物の修繕義務は、
原則 賃貸人にあります。
例外 賃借人の責任で修繕が必要となった場合には、賃貸人は修繕義務を負いません。
第606条
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕する義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りではない。
したがって、建物が老朽化していたとしても、原則として賃貸人には、修繕義務があります。
どの程度の修繕義務を負うのか
基本的には、契約で定められた使用目的に沿った使用に支障が生じているときは、修繕義務があるといえます。
そして、修繕義務があるといえるのは、修繕が可能な場合に限られ、修繕が可能か否かは、物理的・技術的のみならず、経済的な観点から見て決すべきものと解されています。
築年数が経っている建物は、築年数に応じて相応の朽廃が進行していることは当然ですので、築年数に相応する程度の使用に支障が生じているときは、修繕義務があるといえます。
ただ、修繕が必要だといえる場合でも、修繕に多額の費用を要するもののうち、現状のままでも借主側の受ける損失が小さいものにあっては、借主において現状を甘受しなければならないものもあるといえます(東京地裁平成3年5月29日)。
その他、次のような裁判例があります。
東京高裁昭和56年2月12日
もともと賃貸人の修繕義務は賃借人の賃料支払い義務に対応するものであるところからして、結局は賃料の額、ひいては賃料額に象徴される賃貸物の資本的価値と、欠陥によって賃借人がこうむる不便の程度との衡量によって決せられるものと考えられる(なおこのことは破損、欠陥が契約成立後に生じた場合も同じであって、その修繕に不相当に多額の費用、すなわち賃料額に照らし採算の取れないような費用の支出を要する場合には、賃貸人は修繕義務を負わないことも同じ理に基づく。)
具体的には
具体的な事案に応じて、修繕義務があるのか否かにつては判断が難しいところではあります。
この点、前掲の東京地裁平成3年5月29日の裁判例においては、賃貸人(被告)から、修繕に賃料の3年分の費用がかかるため、修繕の履行を求めることは権利濫用だとの主張がなされましたが、
「被告が出捐を要する費用は、少なく見積もっても被告が原告から支払われる賃料の数カ月分を超えることが明らかであるが、右程度の支出を要する状態では修理不能の域に達していると認めることはできず、さらに前記認定しているように、水洗便所の工事費の負担のほか、本件建物新築以来、被告を含む賃貸人側では本件建物の修繕費を支出したことがない等のであるから、今回の支出がある程度の額となっても、それをもって賃料との均衡を欠くものとすることはできない(賃料との均衡を失するというのであれば、未だ立て直しの時期が到来していない本件建物にあっては、賃料の増額の方法によって調整されるべきである)」
として、賃貸人からの権利濫用の主張を退け、賃貸人の修繕義務を認めています。
結局のところ、賃料に比較して不相当に過大な費用を要する修繕については、賃借人に不都合が生じていたとしても、賃貸人の修繕義務が否定されるといえますが、不相当に過大といえるか否かの判断は、厳格に解される傾向にありそうです。
修繕義務を負わないことの特約
そうすると、賃貸人としては、初から修繕を負わないことの合意をしておきたいところですが、このような特約は有効でしょうか。
修繕義務を負わないことの特約の有効性
賃貸人の修繕義務を定めた民法606条は、強行規定ではないので、賃貸人が修繕義務を負わないことを定めた特約も有効です。
ただし、建物を使用させるということ自体は、賃貸借契約の本質的内容ですので、雨漏りや柱など、建物の本質的構造に関する部分についても修繕義務を負わないとする合意は、合理性を欠き無効であると解されます。
賃貸人が修繕義務を負わない=賃借人が修繕義務を負う ではありません。
前述のとおり、原則として賃貸人が修繕義務を負わないことの特約も有効です。
しかし、だからといって、賃借人が当然に修繕義務を負うわけではありませんのでご注意ください。
では、特約で積極的に、賃借人に修繕義務を負わせることはできるのでしょうか。
賃借人が修繕義務を負うとの特約の有効性
賃借人が修繕義務を負うとの特約も、有効です。
ただし、大修繕について賃借人に修繕義務を負わせる内容の特約があったとしても、前述のとおり、大修繕については賃貸人が修繕義務を負うべきといえますので、大修繕について一方的に賃借人に修繕義務を負わせることは、合理性を欠くものとして合意のとおりの効力が生じないと考えられます。
また、賃借人が個人の場合には、賃借人は消費者契約法上の「消費者」に該当しますので、消費者契約法の観点からも無効とされる可能性があります(消費者契約法第10条)。
名古屋総合事務所の詳しい情報はこちら